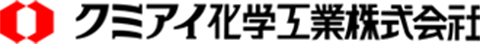保安防災・労働安全衛生の推進
方針・考え方
「安全衛生」とは、従業員が安全で健康的な環境で働くことを確保するための取り組みであり、企業の持続可能な成長を支える基盤であり、企業経営において優先すべきマテリアリティです。化学メーカーでは、取り扱う化学物質や作業環境において、より高いレベルの安全衛生管理が求められます(レスポンシブル・ケア)。事業所では、安全衛生委員会が中心となり従業員の安全衛生への関心を高めるとともに、従業員の意見を反映し、災害防止対策ならびに健康の保持増進活動を推進します。本社では日本化学工業協会の労働安全衛生部会や化学防護手袋研究会への参加、労働安全コンサルタントとの契約、大学教授との共同研究など、社外の団体・有識者とのつながりをもった活動と各事業所のサポートをします。社内外の協力のもと、全社的な安全衛生活動を推進します。
安全衛生管理体制
当社では事業所ごとに総括安全衛生管理者を任命し、以下の事項を総括管理しています。
- 従業員の危険または健康障害を防止するための措置に関する事項
- 従業員の安全または衛生のための教育の実施に関する事項
- 健康診断の実施、その他健康管理に関する事項
- 労働災害の原因の調査および再発防止の対策に関する事項
- その他、安全及び衛生管理に関する事項
また、安全衛生委員会を設置し、従業員の安全衛生に関する関心を高めるとともに、従業員の意見を反映させ、災害防止対策ならびに健康の保持増進を向上させる活動を推進しています。各事業所では必要に応じ管理者・責任者、産業医等を選任し、安全衛生に関する業務を遂行しています。
さらに、2024年度からは、本社(レスポンシブル・ケア推進課)で各事業所の活動をサポートするために以下の対応を始めました。
- 安全衛生活動の進捗、成果の可視化および活動の振り返りを容易にするために、年間安全衛生計画表の様式を変更し、統一する。
- 社内グループウエアを利用し、各事業所の安全衛生委員会報告の情報共有を図る。
労働災害を抑止する取り組み
発生した労働災害について、発生状況や根本原因を解析し、再発防止対策を立案・実施しています。また、災害発生状況や改善点などを報告書に取りまとめて管理しています。報告書は、社内グループウェアを利用して各事業所と共有することで、類似災害の再発防止に役立てています。
労働災害発生件数(新規)
| 年度 | 通勤災害 | 業務災害 | 全体 | 内休業災害 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 2022 | 4 | 15 | 19 | 1 |
| 2023 | 1 | 6 | 7 | 1 |
| 2024 | 7 | 16 | 23 | 8 |
| 合計 | 17 | 42 | 59 | 10 |
- クミアイ化学単体の直接雇用者を対象
安全衛生に対する取り組み事例
レスポンシブル・ケア推進規程の新設
「レスポンシブル・ケア推進規程」を会社規定に新設しました。この規定はレスポンシブル・ケア(RC)推進委員会の構成、運営、推進体制、RC推進委員会ワーキンググループ、労災・事故対策検討グループについて必要事項を定めることにより、レスポンシブル・ケア活動の速やかな対応に資することを目的とします。
労災・事故対策検討グループ
「重大な労災および事故が発生した場合の迅速な業務再開に向けて、当該部門に加え、第三者的立場で、再開の可否を適切に判断・承認するシステムが必要」とのトップマネジメントからの指示を受け、「労災・事故対策検討グループ」の設置について定めました。
労災・事故対策検討グループは、部門が主体となる運営事務局・顧客対応・原因調査・再発防止等のチームで構成されます。そして、第三者的立場として、専務執行役員直轄の部門であるサステナビリティ推進部が本社対策チームとして加わります。外部専門家の助言も得て事故原因解明および適切な安全対策の構築を行い、さらに作業手順書の見直しや作業者の安全教育も行います。
HAZOPの導入
化学合成プロセスにおける爆発火災リスクアセスメントの手法として、HAZOP※を導入しました。導入にあたり外部専門家とサポート契約を結び、2日間の講習・演習を受講しました。現在、破裂事故があった静岡工場の第4プラントから取り組みを開始し、全プラントへの展開を図ることで、工場全体としてさらなる安全性向上に取り組んでいます。
- HAZOP(Hazard and Operability Studies):複雑なプロセスや装置に対する安全性評価手法の一つ